出席者:千野貴裕(司会、教員)、大内佑介(教育学研究科修士課程二年・社会科学専修卒業生)、北嶋健治(社会科学専修助手)、長島彩(社会科学専修二年)、永田爽真(社会科学専修三年)
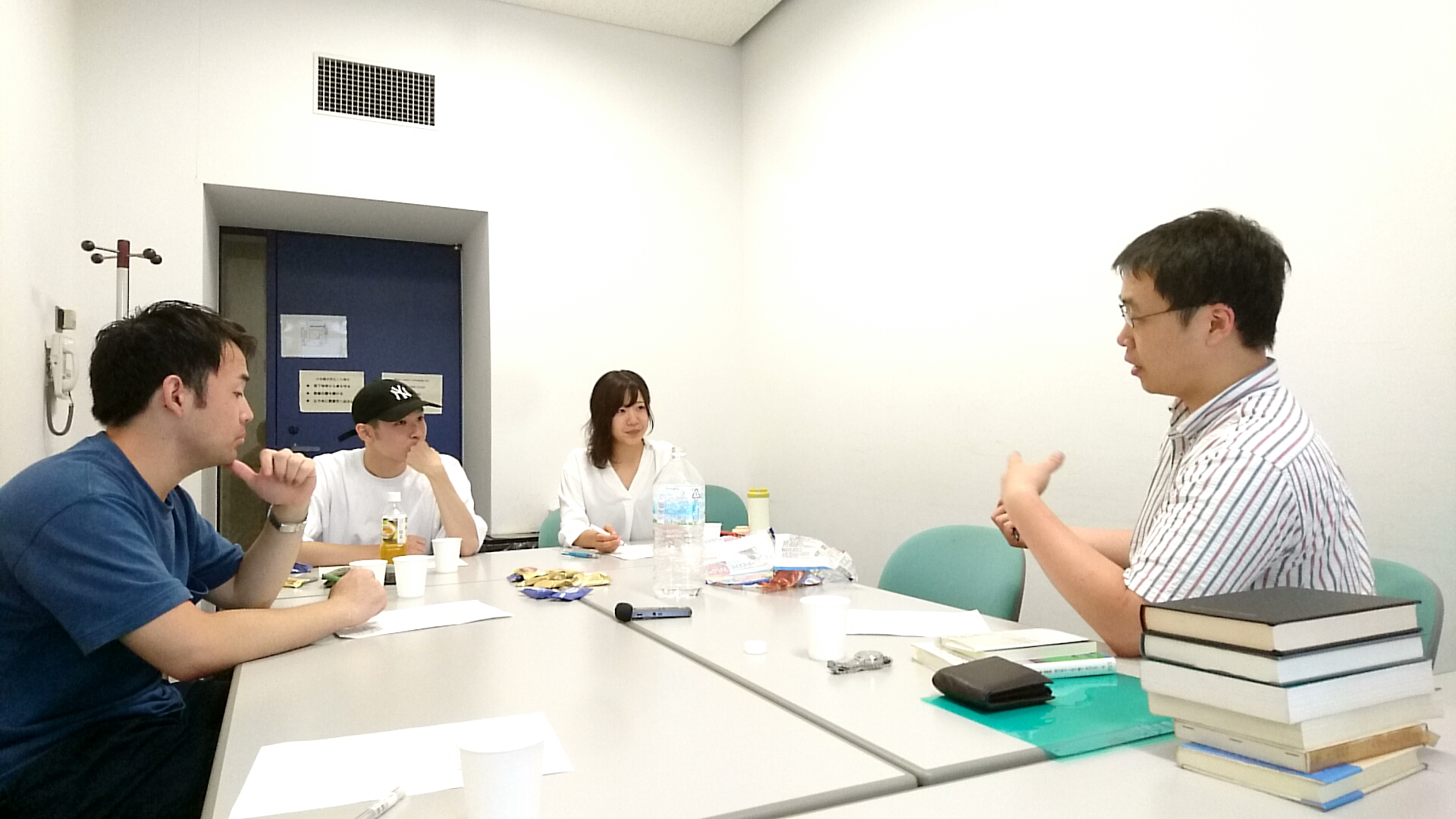
社会科学専修での学びと生活
千野:
政治学・政治思想史を担当している千野貴裕です。皆さんご存知の通り、教育学部社会科社会科学専修は2018年度入学生より「公共市民学専修」と名前を変えます。名前だけでなく、カリキュラムも大幅に変わります。なぜ変わるかというと、現代の社会をとらえる観点はさまざまあるだろうけれど、ものすごいスピードで多様化し、ある意味では不安定であり、しかし広くかつ新しい価値観に潜在的に開かれている今後の社会を生きていく上で、「公共性」と「市民」がとくに重要な概念になるだろうと考えられるからです。本日は、社会科学専修の現役学生、あるいは卒業生の皆さんにお集まり頂き、この「公共性」と「市民」という二つの概念をキーワードにしながらも、それにとどまらず、社会科学専修で良かったと思うこと、もっとこうして欲しいことなど、ざっくばらんにいろいろとお話し頂きたいと思います。そうすることで、いろいろな意見を反映しながら、私たちの新専修である、公共市民学専修の展望を描いていければと思っています。今日はよろしくお願いします。それでは、まず簡単に自己紹介をして頂き、そのなかで興味関心についてもお話しくださいますか。
大内:
教育学研究科社会科教育専攻修士2年の大内佑介です。大学時代は教育学部社会科社会科学専修に所属していました。専門は社会学で、大学時代も現在も若林幹夫先生にご指導いただいています。修士論文のテーマは現代社会における「夢」の意味や機能についてです。
「夢」っていう言葉は色々な意味合いがありますが、その中のひとつに「将来実現したい事柄」っていう意味があります。人が夢を志したり追いかけたり、叶えたりする現代社会のなかで、夢っていうのは単純に将来実現したい事柄という言葉としてのみ存在するだけでなくて、人を何か行動を駆り立てて、場合によってはその人の人生を大きく変えるわけで、そう考えると社会のなかで夢っていうものが何かしらの機能を持っていると考えることができます。では、どういった機能を持つのか、ということについて論文で書いています。
卒論もその関連で書き、若林先生に修士もこのままやるといいと言われ、僕もそのままもう少ししっかりやろうということで、今修士論文を書き上げている最中です。なかなか難しいのですが。
千野:
面白い研究ですね。その分野で、大内さんが参考にし、あるいは批判することで研究を発展させていけるようなもの、つまり「先行研究」はあるのですか?
大内:
夢についての先行研究があるわけではないので、それこそ近代・近現代論、ギデンズ(イギリスの社会学者)等を援用しながら議論を進めています。あとは若者研究とかですね。
千野:
さまざまなデータも収集しないといけないと思いますが、インタビューなどはしていますか?
大内:
データとしてはインタビューを出していくので、またそれをどういう風に提示していくのかという問題がありますね。今そのインタビュー調査を夏休みやりながら、という感じです。
永田:
3年の永田爽真といいます。社会科学専修に入ったのはもともと学校の先生になりたかったのと、教育学や政治教育を学びたかったからです。いまでも好きで本を読んだりするのですが、そのなかでいろいろなことがあって、急に政治理論や政治思想が好きになって、そういうことについての本を読んでいます。まだ3年なのですが、大学院生や他大の学生と読書会をやって、そのなかでいろいろ考えたりしています。特に最近はラクラウ(アルゼンチン出身の政治学者・思想家)読んでたりしたのですが、もともとはフーコー(フランスの哲学者)が好きで、結構バラバラな感じです。

長島:
2年の長島彩です。1年生の頃は国語国文学科にいたんですけど、社会問題に昔から興味あったんですけど、偶然声かけられて入った海外ボランティアサークル(NPO法人 Habitat for Humanityの傘下にある、WHABITAT)にすごく興味を掻き立てられたので、やりたいこと変わっちゃったなって思ったら、転科というものがあるということを知り、じゃあ転科しようと思って社会科学専修に来ました。そのサークルでは、海外住居建築ボランティア、海外に行ってお家を建てるということをやらしてもらっています。社会科学専修の授業はすごい面白くて、社会問題とか、ホームレスの話とか、ゼミの若林幹夫先生は都市論についてお話してくれるので、その話がすごい面白いです。今は知識を吸収している段階なので、今日の座談会でも先輩方や先生方のお話を聞くのを楽しみにしています。
千野:
海外はどういう国に行かれましたか?
長島:
今まで行った国一カ国しかなくて、ルーマニアでお家を建ててきたんですけど、今週末からスリランカに行ってお家を建てる予定です。東南アジアだと東ヨーロッパと結構違っているみたいなので、サバイバルしてきます。
千野:
家を建てると言っても地域によってスタイルも全然違いますよね。
長島:
スリランカではすぐ壊れそうな家を建てるんですけど、一週間行くだけで30人のチームで4軒は家を建てます。どうせ水害で無くなるから、そんなにしっかりしていない家でいいんだという発想だということです。じゃあ水害に耐えられる家は建てないのかなと聞いたら、それを建てるコストがないっていう返事でした。
千野:
あくまで現地の人の発想に合った家を建てるってことですね。その海外ボランティアのサークルに出会ったきっかけって何だったんですか?
長島:
大隈銅像の目の前で、先輩が「海外ボランティアに興味ありませんか!?」「あります!」って(笑)。それでお話を聞いていたら、「家建てようよ一緒に!」って言われたので、「行きます!」って答えました。その年の夏に「ルーマニア行く」って先輩に誘われて行って、すごかったです。現地の人が英語喋れない人ばっかりなので、日本語で話すしかないから、あっちはルーマニア語、こっちは日本語でしゃべりました。そういうときに思ったのが、日本で活動していると、早稲田生とか大学生とかそういうレッテルがけっこうコミュニケーションにかかわってくるけど、あっちでいったら家を建てる能力があるかどうかとか、体力があるかどうかとか、そういう感じでしか見られないから、縛られているものが少なくて、とても楽だったし、できる経験も日本ではできないことがたくさんあっておもしろかった、ということで続けています
千野:
18歳で「自分のやりたいことがこれだ!」って決まっている人はむしろ少数かもしれないですよね。大学受験の時点でやりたいことが分からなかったり、あるいはやりたいと思ったことがいろいろなことを経験したり考えたりするなかで変わっていくというのは普通のことだと思います。私も歴史学をやろうと思って大学(ICU)に入りましたが、気付いたら政治思想史をやっていました。そういう意味では、転科ができることも教育学部全体のいいところだと思います。教育学部には文系理系を問わず幅広い学科専修がありますし、さらに社会科学専修のなかにも幅広い学問分野が皆さんを待っています。ですから、社会科学専修の皆さんの多くは、入学した時にぼんやりと思っていたやりたいことと、卒業の時に取り組んでいる分野は違っているのかもしれません。
ところで、長島さんがおもしろいことを言ってくれました。私もイギリスに四年、イタリアに半年いたので経験がありますが、海外に出た時に、自分も当然のものだとして受け入れている社会的属性、もっと言ってしまえば社会的立場ですかね、そういうものが関係なくなることはままあります。日本でどの大学にいたとか、どう評価されたとか、そういったレッテルは関係ないですし、そもそも日本の大学のことなど海外の人は知りません。学期が春から始まることとか、大学教員の忙しさとか(笑)。
むしろ、そうしたレッテルが無化されたところからお互いのコミュニケーションが始まるわけですね。長島さんが経験したように、家を建てれるかどうかとか。実は、海外に出なくても、皆さんの日常のなかでもそういうレッテルを問い返すような経験はあると思います。サークルやバイトとか、授業の外で自分が揺さぶられるような、あるいは決定的な疑問をもつような経験をして、それが自分の人生設計や考え方を大きく変えるきっかけになったりすることはあるんじゃないでしょうか。教員としては、それを社会科学専修の授業で学ぶこととそうした経験を結びつけてくれると良いなと思うのですが、皆さん、そういう経験はありましたか?

大内:
僕はとある予備校で大学4年間アルバイトをやっていました。そこの予備校でもちろん勉強もするんですけど、それ以外にも「君の夢は何なんだ?」という風に問いかけたり作文を書かせたりして。例えば弁護士になるなら、「君は法学部に行って司法試験に合格してっていうのが必要だから、法学部に行かなきゃ行けない。だから勉強しなきゃいけない」という風に、一番未来の彼方に夢を置いて、大学受験を中間地点において、現在の高校生という時間を手段化していく・・・という言い方をしたら確実にその予備校に怒られると思うんですけど(笑)。実は僕も高校生のときにその予備校に通っていて、当時同じ質問をされて、それがすごく嫌だったんです。僕は野球部だったので、「夢は何?」って聞かれた時に、「甲子園に行きたい」って答えたら、「いやそうじゃなくって」みたいに言われて。そのときから、「弁護士になりたい」みたいに、何で職業で答えなきゃいけないのかなという疑問があって。それで大学に入って、予備校のスタッフ側になって、自分が生徒にそれを聞かないといけないというときに、「何か夢とかあるの?」「ありません。」「そうだよね、ないよね。」とかなったりして(笑)。その中で、これはいったい何なんだろうって思った結果、最終的に修士まで行くことになりました。卒論で書いたんですけど、もうちょっとちゃんと書きたいなっていうのがあったので。そのアルバイトをしてなかったら今論文書いてないですね。
永田:
僕はバラバラなことやっています。サークルとかはやってなくて、バイトも特に何も考えずにやっています。さっき経験の話が出ましたが、僕は多分ここの受験生や下級生に勧めたいことってことで話したいと思ったのは、色んな経験をしたほうが良いということです。大学にいるとすごく忙しくて、何となく過ごすと結構過ぎていってしまう環境がすごくあると思います。そのなかで大学にいると色んな友だちができて、楽しくて、サークルで同じ大学生だけとか、それもいいことだけど、僕なら大学の外の地元の友だちと遊んだりとか、いろんなことをやっていくなかで経験を増やして欲しいっていう部分があります。そういう人たちと、音楽をやったりとか、ミュージシャンの仲間だったりとか、あと古着が好きだから古着屋の店員さんと仲良くなったりとか。あと読書会とか、色んなところに環境があります。そういう風に年齢も属性もバラバラなところでは、色んなところでもできる。そういう経験を大学生活につなげていって欲しい。経験していくと何が重要かっていうと、経験だけじゃ全部語れないってことが分かる。経験の有限性っていうか。経験で色んなことを語りがちだし、それが大事っていうのももちろんそうなんだけれど、そういう有限性みたいなものをみんなに気づいて欲しい。
千野:
今の、大内さんと永田さんのお話はリンクするところがあると思います。今大内さんがしてくださった、その予備校で言われた「夢」って、いろいろ悩んだりあっちこっち行ったりしてその中で自分自身のもつ価値観をビルドアップしていくって考え方とは対極的ですよね。最初から「夢」があって、しかもそれは社会的属性と密接不可分であると。大内さんはそこに疑問というか違和感を抱かれたんじゃないかと思ったんですけど、どうですか?
大内:
話は変わってしまうかもしれませんが、夢の研究をしていると分かってくることは、「今楽しければそれで良い」というコンサマトリーな思考をとる若者が増えてきていると言われることがあって、実際に生活意識調査でもそういう傾向がでているというのがあるが、夢を目指して努力するという考え方はそういうコンサマトリーなものと対極に置かれる、あるいはいろいろ経験してその中で何か自分で見つけるというのと対極に置かれる一方で、夢を見つけて夢を叶えなさいという人は、夢を見つけることを強調するんです。夢を見つける作業がまず大事で、そのときに色々な経験をしなさいと言うので、夢ができるまでの段階においては結構同じなのかなと。色んな経験をして、夢を語る人って何かしら自分が夢を見つけたきっかけを語る傾向にあるので、そこの段階、最初の夢を見つけるところまでは共通していると思います。
千野:
大学生になると生活の自由度が増えるじゃないですか。大学に入って経験したり考えたりすることの質に鑑みると、高校生の段階で人生の目標を定めて、そこに向かって積み上げることを逆算して、そのひとつとして受験勉強を位置づけるというのは結構難しいんじゃないかと思います。先ほども言いましたが、大学に入った後に自分のやりたいことや興味がどんどん変わっていくっていうのは、私は普通のことだと思います。皆さんに聞きたいのですが、高校生の時に自分がこうしたいって思っていたのと今の自分の姿はやっぱり違いますか?
永田:
僕が高校生のときは、周りからマセガキって言われてて、色んなとこに顔出すタイプの人間でした。音楽やってたり、先輩たちと色んなことやったり、あんまり学校一つに囚われるタイプの人間じゃなくて。だけどやっぱりそれって色んな選択肢広げていくと悩むことも増えてきて、これからどうやって生きていこうってことを悩みすぎて、高校が全然楽しくないまま終わるっていう、そういう生活でしたね。考えすぎて、もう無理やっていけないって思って、とりあえずあらゆることに反発しすぎて、受験勉強とかも、絶対しないって言って、結局1年受験しませんでした。その後に色々考えたんですけど、やっぱりそういう風に高校生の頃からずっと色んなものを押し付けられることもあるし、選択肢が広かろうが狭かろうが、大人たちから。それに多分高校生当時の僕は耐えられなかったと思うんですよね。だからあんまり良いことは言えないんですけど、夢だけじゃなくて色んなことを押し付けられる社会のなかで、それに対してきついって思ってる人は多いと思います。それは高校だけじゃなくて、大学生になって就職活動するときに、そういう風に考える人も増えてく。だから、そうならないようにじゃなくて、その時に何ができるかっていうために、いろいろな経験が生きてくるはずだと思います。
長島:
私ほんとに対照的なんですけど、高校のときは遊んでしかいなくて。将来のことなんかほぼ考えてなかったんですよね。これからどう生きていこうとか考える前にカラオケに行こう、みたいな。カラオケに行って歌って、寝よう、みたいな。それでカラオケとバイトしかしてなくて、一浪して、その時に、小学校のときからお世話になってた美容室のお姉さんに、「彩の人生って何も頑張ってないね」って。「カラオケ行ってバイトして、それで終わっていいの?」って。髪切りながらそんなこと言う?みたいな(笑)。
一同:
(笑)

長島:
小学校2年生から私の成長見ている人がそう言ってきたから、確実に私そうなんだって、すごい悔しくって、ちょっと頑張ってみようかなって思って、早稲田を第一志望に置いたら、勉強する楽しさとかをその時に予備校の先生が教えてくれて。その時に、世界史の先生が与えてくれた影響がすごく大きかったと思うんですけど、「自分たちが社会を作ってく一員なんだ」なっていうのを色んなことを通して伝えてくれる先生でした。その時に、将来の夢とかまったくないんですけど、夢があってもなくても、自分が社会を作ってく一員になってくってことは確実じゃないですか。その時に何か社会に良い影響を与える人間ではありたいなっていうのは、その先生の影響なんですけど、ずっと思っています。いま社会科学専修に転科できて、そこで先生がしゃべってくれる色んな知識とか、あとサークルでスリランカに行くプロジェクトの副代表をやっていて、チームのメンバーをマネージメントしていく上で、みんなとのコミュニケーションの取り方とかいろいろな経験や勉強をさせてもらっているから、自分が社会に出たときに、社会科学専修で学んだ、社会的・社会科学的なものの考え方っていうのを活かしていける、そういう風な知識を自分の中ででつけていけたらなと思ってるんですけど、全然よく分かってないですね(笑)。
「公共性」と「市民」
千野:
三人の話を聞いていて非常に印象深かったのは、学校外での出来事が何がしか自分が今に至るまでの道筋をつける上でのインパクトがあったということだと思います。大内さんでしたら予備校での経験が大きかったと思うし、永田さんなら音楽とか、高校のときの友だちや煩悶とか。長島さんは美容室のお姉さんとか高校のときの予備校の先生の話とか。そういう学校外での出来事が皆さんの今の現在地点に影響を与えてるんじゃないかと思いました。
この話からそろそろ本題に入りたいのですが、公共性と市民という二つのキーワードについて話していきましょう。まず公共性ですが、この言葉には大きく二つの意味があると思います。ひとつは「開かれている」こと。openであるということですね。公共という言葉自体は江戸時代からありますが、近代的な政治学あるいは社会科学の概念としての公共性は、ドイツ語に由来する言葉で、ドイツ語だとÖffentlichkeitです。offen、つまりopenということ、開かれているということですね。あらかじめ境界線が設定されていて、資格のある人しかこの境界線の内側では活動してはいけませんということでないという意味で、他者に対してopenだと言えます。
公共性のもう一つの意味は「共通している」ということです。他者に対して開かれていながら、その開かれた中で誰かと出会って、そこで何かを共通したもの、例えばある空間や時間、経験や考え方や悩みであるとか、そうした何かをお互いに共有するということがありえます。
公共性にはこうした二つの基本的な定義があるのですが、その二つ、つまり、①他者に対して開かれているということと、②他者と付き合って何かを共有するということは、どちらも市民という言葉とも関係すると思います。先ほど長島さんが、われわれが社会を作っていく成員だと言ったこととも関係します。皆さんはこうした言葉にどういうイメージを持ちますか?
長島:
国民が、主権国家の中で国を形成している要素というのと対照的に、市民というのは、国を形成していく上で、他者の意見を交換して、話し合って、国を作っていく政策とかに関わっていく要素、というイメージがあります。
永田:
僕もそのように考えます。あとは政治参加とか。自ら議論することと共に、それに関してどう行動していくかとか。それは社会の一員としてどう作っていくかっていうところがあるかと思います。でも国民と市民って似ているところもあると思う。市民権というところでは国民が持つ与件であるところもあるし、かといって、日本には無いが、外国人の地方参政権とかというふうに考えていくと、市民権は国民という与件とは違ってくるなと。
千野:
デニズン(denizen)という言葉は聞いたことはありますか? 市民権(=シティズンシップ、citizenship)というと国政参政権や地方参政権や社会保障をすべて含むフル・シティズンシップを思い浮かべるかもしれませんが、例えばEU市民権を持っているイギリス在住市民はイギリスの国政参政権はありません。もちろんイギリス在住のEU市民は所得税や住民税などの税金を取られます。イギリスの社会保障はちゃんと受けられるし、当然自分たちが住んでいるところの代表を選ぶ権利、つまり地方参政権はありますが、国政参加権はありません。デニズンというのは、こういう部分的なシティズンシップを持っている人々のことです。今永田さんがおっしゃったことはこうした考え方と近いのではと思います。大内さんはどうお考えですか?
大内:
市民という言葉のイメージについて、お二人がおっしゃったことと重なるところはあるのですが、それ以外のところで言うと、単純な「民」というところで考える。民と市民ってどう違うのかということについては、自分の中で市民というのは見識・良識を持っている、そう言うと抽象的な表現になってしまうのですが、それらを持った上で、主に政治的なことの判断を個人としてできる、あるいはそうした能力を持っている人のことを指すのかなと。また群集とかとかとなるとちょっと話が違ってくるのかなと思います。
千野:
市民は一方で国民と重なる部分もあるのだけれども、概念的には区別することはできて、他方で、無定形な群集とも違うということでしょうか? 突然話を振って悪いですが、同じく社会学をやられている北嶋さんはどうお考えですか?
北嶋:
少し違った観点からすると、市民というのは、国家が個人を特定する際の単位である、そういう側面があるとも言えます。例えばトーピー(アメリカの社会学者)やライアン(カナダの社会学者)が指摘するように、国民や市民という概念は、潜在的にはですが、生活し移動する個人を特定する際の単位としてもあった。一方でそれは人々の自由のための条件としてあるのですが、他方でそれは行政の上で人々をシステマティックにまとめる上でも発達してきた。こう言うと少しネガティヴに響くかもしれませんが、この点で人々は市民として自由でありつつも、その言葉に責任をもって行動していく、そうした必要があるとも言えます。

千野:
つまり例えばアメリカだとソーシャル・セキュリティナンバーを持っている人びとはその制度の恩恵にも預かるけど、同時に行政から補足されやすくなるということですよね。パスポートもそうでしょうか。出入国を厳密に管理することは比較的最近になって始まったことです。今説明してくださった観点から見ると、例えばパスポートを通じて出入国管理することは、ある国の国民だけでなくその国から見た外国人も含めて、世界大の行政管理システムとして機能しているわけですね。
長島:
デニズンシップって多国籍の人に有利な形で使われてるということなんですか?
千野:
もう少し詳しい話をすると、20世紀の初頭まではある国の国民であるということと社会的な権利を受けるということは同じことでした。例えばイギリス人であることは、イギリスの社会制度の一員であって、イギリスに税金を納めてその社会福祉一般や教育や国民皆保険制度の恩恵を受けられることを意味しました。国民単位で社会保障制度があったということです。現代のように事実として非常に社会が多様化し、人の移動も激しくなると、国民という単位だけでは捉えられなくなってきます。国民ではないのだけれどそこに住んで、労働をして税金を納める、そういう人が社会保障を受ける権利をどういう風にカテゴラライズしたら良いのかということを考える必要が出てきます。デニズンはこのことを可視化する概念ですので、その意味で国民とは区別されるということです。
みなさんの言ってくださったように、国民と重ねる部分もあるのですが、そこから切り離して市民という概念を考えて見ると、みなさんは国民的とは形容できないような、つまり市民的としか形容できないような活動というか行為を多かれ少なかれしている部分があるのではないかと思います。例えば、さっき長島さんの言ってくださった社会を作る一員という意識は、国境を飛び越えているわけですよね。他の国やそこに住む人びとのこともその意識の対象に含まれてくるわけです。そうしたことが自分の顧慮の範囲に入り、またそれが自分の経験の一部を構成するようになるわけですよね。
そう考えていくと、みなさんがやっていることは市民的だし、さらに言えば公共的でもあると思います。公共的というのは、先ほど開かれていることと共通しているということだと言いましたが、このことを反対側から考えてみると、自分自身の利害や価値判断をことさらに強調すること、自分自身のことだけを考えるということではない、ということではないかと思います。例えば、大内さんが夢の研究をしていらっしゃる。それはご自分がよく知りたい、もっと理解したいということもあると思いますが、研究活動は極めて公共的ですよね。研究成果は他者に対して開かれているので、色々な人が大内さんの研究成果にアクセスして、それを共有できる。開かれていると同時に共通しているわけです。永田さんのやられていることもそうですよね。音楽は参入障壁があるかもしれませんが(笑)しかし例えば、自分自身のことだけ考えていたら社会運動は成り立たないわけです。ただ、もちろん利他主義ではなくて、自分も含めた多くの人の身に起こりうる社会的課題を他の人びとと共有し、そうした問題に光を当てるということだと思います。先ほども触れましたが、長島さんのやられていることもそうですよね。そこでみなさんに聞いてみたいのは、自分のやっていることのモチベーションというか、何でそういうことをやろうと思ったのか、ということです。難しい質問だとは思いますが、大内さんは何で今の研究をしようと思ったんでしょうか?
大内:
何で研究しようと思ったかという問いに対する答えで、それに興味があるからという答えだと答えたことになってないので、もう少し言うと、僕個人の人格に関わることだと思うんです。僕は人情の機微というか、人の心の微妙な揺れ動きというのが好きで、人のエゴを見るのが好きなんです(笑)。もう少し荒っぽく言うと、人の醜いところを見るのが結構好きで、でもそれをあざ笑うんじゃなくて、それを見ると「ああ、人間だな」って思うので、そういうのが好きで。夢の研究もそうなんですけど、夢、夢って言いながら結局今この現実をどうにか肯定しようとする。「夢があるから今頑張れるんだ!」とか言って、どうにかして夢も希望もないつらい現実の中で自分を奮い立たせていくというか。そういう人たちの話を聴いて、純粋に面白いなって思うんです。やっぱり自分がどうのこうのというよりも、人のことを見て面白いなと思うので、どうしても自分のことだけ考えるってことにはならないのかなと。逆に言うと、自分が、自分が、ってなってる他人を見るのは好きですけどね。

千野:
人間理解という意味で、他者に関する関心がご自分の自己認識と不可分に存在しているということでしょうか。永田さんはどうですか? ところで、先週行った教員座談会でも、学生のなかには自分の狭い属性などに閉じこもって、他の人とコミュニケーションすることが苦手ですというふうに、最初から予防線を張っているケースが見られるという話を聞きました。教員と学生の距離も遠くなってしまっていて、あまり研究室に来て教員と話すことも少なくなったという話も聞きました。気にせずに、もっと行っていろいろな話をしたらいいと思いますが(笑)
永田:
あまり偉そうなことは言えないのだけど、そういう人たちにはもっと面白い世界が世の中にいっぱいあるってことを知ってほしい。ホント音楽なんて無限だから。みんな聴こうよ(笑)。なかなか聴いてくれないのは何でだろうと考えると、やっぱり異なる世界の人たちと関わることが少ないからかなと思いました。ぼくなら音楽を知るのは音楽の世界だけじゃなくて、音楽を聞く本好きとか、古着屋の人とか、音楽を知るのが目的ではないのだけど何かつながるところがあると僕は思っていて。音楽だけではなくて、一人ひとりがそういった交流の中でなにかを見つけることができれば、もっと面白い世の中になると思います。
千野:
長島さんいかがですか?
長島:
いま永田さんが言ってること聞いて、「分かるわ~」と思ったんですけど、正直ボランティアとかやっても自分が他者のこと考えて生きてると思ったことなくて、ボランティアを始めたきっかけっていうのが、お父さんの言葉でした。お父さんずっと北海道の田舎の医療崩壊が進んでるところで、ほんとおじいちゃんおばあちゃんしかいないところで、おじいちゃんおばあちゃんしかいないから、正直亡くなる方のほうが多くて、だから終末期医療に関わってるんです。それで、患者さんを看取られる時に、そこに寝てられる患者さんがいて、その人が息を引き取ったその瞬間に、うわって周りの家族が泣き出す人と、一人で誰にも病室で見守られないまま亡くなっていく人もいる。きっと人間のやってきたことっていうのは最後の瞬間に出るんだってお父さんに言われて、その時に、結局人と人って一緒にいないと生きていけなくて、そういう人生の最後の時に出る、自分が何をしてきたかっていうのは、わたし的には、人と築いてきた関係みたいなものが残っていくんだなって思っていて。永田さんが言っていたみたいに、自分ひとりの人生だけで出来ることとか知れることとか経験できることとって限られてるけど、人と話すことで、そういう経験や世界があるんだって、本読んだりとかもそうですけど、知ることができる。世界が広がっていくっていう感覚があるからこそ、ボランティアとかこういう座談会で永田さんとか大内さんとかの話を聞いたりとか、ゼミに行ったりとか、というのがただ単に面白いし、いろんな人たちと関係を築いていけるのも素敵だなって思ってやってるんだなって思います。
千野:
お父さまは今も終末期医療をやってらっしゃるんですか?
長島:
はい。私が7歳の頃から。

千野:
私がみなさんの話を聞いていて思ったのは、ご自分でやられてることが、決して自分自身の利害や価値とは背反的ではないということです。繰り返しになりますが、公共的で市民的であるということは利己的であるということとも、他方では利他的であるということとも違うのだということだと思います。これは有名なフレーズですが、アリストテレスが『政治学』という本の冒頭で「人間は政治的動物である」と言っています。どういう意味かというと、人間は自然本性上、一人では生きてはいけないので、人間の本性に従って生きようとすると、人間は共同体を作らなければ生きていけないということです。個々の人間が自足的ではないというところから、人間の共同性、あるいは公共性といってもいいかもしれませんが、その社会的性格の根拠づけを行っています。人間は一人では生きてはいけないと長島さんがおっしゃってたけど、その話と通じるところがあると思いました。
さて、話は尽きないのですが(笑)、そろそろまとめに入りたいと思います。みなさんは大学に対して何かもっと期待することはありますか? 大学の外での経験があって、それと大学の学びが相乗効果を起こしていくっていくというような話は色々ありましたが、それはそれとして、大学にこういうことを望みたいというのはありますか? 場所として、学びの形態として、もっとこういう授業があったらいいとか、こういうことをやってほしいとか。いかがでしょうか。
早稲田大学、そして公共市民学専修に期待すること
長島:
もっとみんなにコミュニケーションとる機会を無理やり作ってくれたら良いと思っています。話し合うということが公共性ということとも関係してくるじゃないですか。意見を交換するって、コミュニケーションってやっぱり練習しないと上手くいかないし、自分から選ばないと、機会を作れないっていうのは、良くないと思っていて。早稲田だと、授業出てレポート出してテスト受けるだけなら、一人で生きていこうと思えば一人で生きて行けちゃうと思います。そういうことじゃなくて、話し合って、意見を交換する練習を大学でさせてくれたら就職したときとかももっと何か意見を上手に伝えられるようになると思います。
永田:
まさに僕はその一人で生活してるタイプの人間で。寂しい(笑)。
一同:
(笑)
永田:
言い訳としては、俺はいろんな場に仲間がたくさんいるって言い聞かせるんだけど、やっぱり大学にももっとそういう場があってほしいと思います。それは、大学が中心という人が多いからですね。もちろんそういう人たちのためにも、もっとそういう場があれば、僕ももうちょっと参入したい。自分で作り出さなきゃいけないんだけど、もうちょっと大学にもやってほしいな、と。その話はわかります。
大内:
せっかく僕だけ大学院生なので言うと、大学院で僕の受けている授業はゼミ形式のものがほとんどで、講義形式のものは基本的にないので、それこそ学生3人と先生一人の授業で、先生がどんどん話を振って、「君はどう思う?」「でもそれはこうだろう」っていうようなことが多いので気づくんですけど、やっぱり人間って、ある程度自分の考えたことに及第点を付けちゃうと思うんですよ。大学、大学院と若林先生のゼミで経験したのが、自分ではちゃんと考えてレジュメを書いて発表したつもりでも、「ここはどうなの?」「これどういう意味?」とか聞かれたときに、あれ、これどういう意味なんだろうとか、自分がここ考えてなかったなとか思うことはたくさんあって。「他の人からするとこの言葉はこういう風に伝わるから、この言葉じゃない方がいいんじゃないの?」って言われることで、ああそうかっていう風になるんですよね。でもそういう機会がない限り、思考も多様化していかないし、深くもなっていかないと思うんで。せっかく大学4年間いるんで、そういう機会って、「ここってどういう意味ですか」とか、「あなたの説明よくわかりません」とかでもいいと思うので、必要なんじゃないかと思います。それこそ、お二方がおっしゃったように、単純コミュニケーションをはじめとして、論じて、それに対してカウンター・アーギュメントがあって、という機会がもっとあってもいいかなと思います。
千野:
授業でプレゼンをすることは、まさに今大内さんが言ってくれたような機会だと思います。それを過不足なく言語化していただきました。公共市民学専修のなかでも、例えば教員がトークセッションをして、学生にフロアに来てもらって、学生と教員が相互にやり取りをする形などを通じてやっていけたらなと思います。おっしゃる通り人と話すということは簡単じゃなくて、色々な失敗をしないと、なかなか上手くなっていかないですね。ところで、公共性論のキーワードのひとつに、「理由」があります。公共的な空間においては、ある人の主張は、日常的権力関係ではなくて、その主張をサポートするために挙げられる「理由」を媒介項としようということです。つまり、理由の妥当性の観点から、あらゆる人の主張は検証されるべきだということです。これは人間同士の対等な関係を考える上で大変重要なテーマなのですが、ただ、さっき長島さんが言ってくれたみたいに、理由の交換は簡単にできることではなくて、一般論としてはトレーニングしないとできないことです。いきなり「その主張の理由を挙げてください」と言われても、難しいわけですね。大学は、そういうトレーニングの場所としての意味もあると私は思いました。
長島:
早稲田はいろんな人いますし。
永田:
本当にそういう場所になってほしいです。教職取ってるので授業が多いんですが、2限から6限まで一言もしゃべらないときある(笑)。
一同:
(笑)
千野:
授業が終わればさっと帰ってしまうとか、あるいはサークル活動に熱を上げるのでももちろんいいのですが、早稲田大学には多くの資源があるので、もっといろいろなことを試す場であってほしいですね。授業内にもいろいろな人がいるので、そこで多くの他者に出会い、友人をつくって欲しいです。あと、専修内外の同好の士が集まって、複数分野の教員も巻き込んで学問分野を横断するような読書会を企画するとか。私自身は、公共市民学専修にそういう機能を期待しつつ、みなさんに伺ったことを反映していけるような専修にしていきたいと思っています。今日はお忙しいなかありがとうございました。
(2017年8月1日)

