参加者:若林幹夫教授(司会、社会学)、伊藤守教授(メディア・コミュニケーション学)、黒田祥子教授(経済学)、千野貴裕専任講師(政治学)

社会科学の研究と「公共」「市民」
若林:
2018年度4月から社会科学専修が公共市民学専修に名前が変わり、カリキュラムも大幅に変わります。この座談会では公共市民学専修になって何がどう変わるのか、公共市民学とは何なのか、私たちが公共市民学専修をどんな専修にしたいと思っているのかといったことを話し合ってみたいと思います。これまでの社会科学専修と同じく、公共市民学専修も法律政治、経済、メディア・ジャーナリズム論、社会学の4分野を基本的な柱としています。そこで今日は、私も含めてそれぞれの分野の教員が集まって、公共や市民ということについて、そしてまた公共市民学とそれぞれの専門とがどう関わるかについて、お話していけたらと思います。
上手い具合に今回は専門分野だけでなく、教員の年齢層も60代、50代、40代、30代と分かれることになりました。社会の見え方、それに学生や大学に関する感覚も、年齢によってちがうかもしれません。
まずはそれぞれみなさんがどんなことを研究していて、公共や市民ということがそれぞれの専門とどう関わるのかについて、自己紹介もかねてお話ください。
千野:
千野貴裕です。政治学が専門ですが、そのなかでとくに政治思想史と現代政治理論を専門にしています。自分自身の研究テーマとしては、19-20世紀にかけてのイタリアの政治思想史を研究しています。イギリスに4年間留学して博士号を取得しました。その後イタリアで研究し、教育学部には今年着任したばかりです。政治思想史と現代政治理論という字面を見るとイメージがつかみにくいかもしれません。政治思想史というのは、過去の哲学者思想家や広く著述家が残したテキストを分析して、我々の社会が、現在を生きている我々が当然だと思っていることを反省的に振り返る学問ととりあえず定義できると思います。我々が考えているような問題、例えば我々はどうしたら幸福になれるのか、我々の社会における善とは何か、そもそもどういう共同体や国家のあり方が望ましいのかといったといった、我々の社会で問われている問題がすでに2000年くらい考えられてきています。こういう蓄積ある思想を学ぶことは、今まで人類が経験してきた様々な難問との格闘の記録を学ぶことですし、われわれはそれを踏まえて、現代の難問(それは過去に問われたことと無関係ではありません)に対して立ち向かう際の十分な補助線になるのではないか、というのが政治思想史の基本的な考え方です。
現代政治理論はその名の通りもう少し現代に寄っています。これは公共的であることと市民であることに関わりますが、誰もが、今現代の自分の視点から見て妥当であるだけでなくて、自分と異なる社会的状況におかれた人の視線から見ても受け入れることができる、そういう意味で理にかなっている社会はどういうものか、その制度はどういうものか、そうした問いを考える学問です。つまり、事実として多様な人間が共通してやっていくためのルール作りを考える学問だと言えるでしょう。理想的と思われるかもしれませんが、政治思想史ないし政治理論がなければ、立憲主義、自由主義、民主主義といった現代のわれわれが共有する社会制度は存在しなかったのではないでしょうか。
黒田:
私は経済学が専門で、特に労働経済学を専攻しています。研究テーマはいろいろありますが、最近手がけているのは賃金に関するもの、もう一つは長時間労働に関する研究や過労が健康にどういう影響を及ぼすかといった研究をしています。
経済学というと、大学であまり学んだことがない人から必ず聞かれるのが、どの銘柄の株を買ったらよいか、景気はいつ良くなるのか、と言った質問で、多くの方がお金のことばかり考えている学問だ、と思っていらっしゃるようです。でも実際は、人間の行動を科学的に考えるというのが経済学の一つの持ち味で、特に心理学と非常に親和性が高い学問だと思っています。
長時間労働に関しては、現在、政府の働き方改革の流れで多くの企業が取り組んでいます。日本では以前からずっと長時間労働が問題だと指摘されてきましたが、なぜ日本人はそんなに長時間働くのかという点にも人間の心理が絡んでいると考えられます。仕事が好きだから長時間労働している、という話をよく聞きます。しかし、本当に日本人は働くことがそんなに好きなのかだろうか、そうではなくてやはり周囲に気兼ねしている人も多いのではないかという仮説を立てた研究を行ったことがあります。具体的には、日本でモーレツに働いていたサラリーマンが、ワークライフバランスが確立している欧州現地法人に転勤になったとき、日本人の働き方は変化するのか、しないのかという研究です。もし本当に働くことが好きだったらきっと労働時間の長さは変わらないはずです。しかし、転勤者のデータを集めて解析したところ、欧州赴任後は、多くのサラリーマンが思い切り労働時間を下げていたり、日本にいる間には一日も有休をとらなかった人が、赴任後に30日の有休を取得していたり、といった実態が見えてきました。つまり、人々は、職場環境とか上司の意向とかを考えながら労働供給行動というのを決めているわけです。
このように人間の心理というものが分かってくると、がんじがらめに「こうあるべきだ」、という精神論で考えるのではなくて、その人間の心理をうまく利用して、インセンティブに働きかけることで人々の行動を変化させ、より良い社会に変えていることができるのではないか。経済学とは、そのようなことを考える学問です。
大学では専門科目として労働経済学を教えています。そこでは今のような長時間労働の話だけではなく、就活の早期化・長期化がなぜ起きているのか、格差是正のために最低賃金を上げるべきかなど、学生に身近なテーマも数多く扱っています。最低賃金については、スタンダートな経済学の考え方では最低賃金を上げると失業者が増えるといわれています。貧困をなくすことを意図した最低賃金の引き上げが、実は一番困っている人の職を奪ってしまう可能性もあるのです。授業では、法律の影響が人々の行動にどう影響し、経済をどう動かすのかといった話や、メディアが格差をどう報道し、それが政治にどう影響するか、といった話もしています。経済学という学問だけでは到底捉えることができない社会全体のメカニズムを色々な角度から勉強していくという、学際的な場に身を置くことのおもしろさを学生に分かってもらいたいと思っています。

伊藤:
専門分野はメディア研究です。日本では、この分野に関しては、様々な名称が付けられています。例えば、マスコミュニケーション研究という名称があります。メディア論や情報メディア研究、最近ではメディア・スタディーズといった名称も使われます。私の場合は、アメリカを中心としたマスコミュニケーション研究というよりは、ドイツのフランクフルト学派のアドルノやベンヤミンの研究、それから次の世代のハーバーマスの研究など一般に批判理論といわれる文脈からメディアを考えるというスタンスでやってきました。この20年近い間は、フランクフルト学派に加えて、イギリスのカルチュラル・スタディーズといわれる研究を吸収しながら、メディアの媒介性について考えてきたということです。最近は、フランスのガブリエル・タルドに関心をもっていますが、フランクフルト学派とカルチュラル・スタディーズという2つが私の理論的バックボーンですね。
いま実際に行っている具体的な研究は4つほどでしょうか。4つの研究課題を抱えてやっています。一つは具体的・経験的な研究で、ニュース分析という領域にアプローチしています。問題関心としては、従来ニュース分析というと、「何が語られたか」という点に分析を加えていくのが一般的だった――言説分析といわれる――のですが、たぶんそれだけではニュース経験は解明できない。スタジオであるとか、テロップであるとか、それからアナウンサーの笑顔や立ち振る舞い、いろんな要素からニュースは作られています。そうした様々な要素が、人々の意識や感情に影響を与えている。したがって、言葉だけでなく、映像や音響など様々な要素を考慮して分析する「マルチモダリティ分析」という視点からニュース分析をおこなっています。
それから、これと関連しているのですが、この間やっているのは、原発や原発事故に関すること、ポスト・フクシマ以降のニュース報道、それからドキュメンタリー番組がどのように今の福島の問題を描いているのかに関しての研究も行っている。
この5・6年の間に急速にメディア環境は変わっています。いまやソーシャルメディアを外しては、私たちの日常的なコミュニケーションを考えることができないくらい、スマートファンに代表されるモバイルメディアが大きな比重を占めてきている。そこで、最近は、学生と一緒に調査をして、FacebookやTwitterをどう使っているとか、そうしたことがらを含めて、ソーシャルメディアを利用した私たちの社会的コミュニケーションはどう変化してきているのか。その問題を考えています。その研究の焦点として、私自身は、アフェクションaffection、情動の問題を中心に据えて、理論的な考察も加えています。
もう一つ第4番目の研究課題ですが、70年代のドキュメンタリー番組の分析を行っています。ようやくテレビ番組もアーカイヴが整備されて、昔の番組について系統的に検証する作業ができるようになってきた。70~80年代にかけて、ドキュメンタリー番組は様々なテーマを取り上げて、記録してきたわけですが、そこで描かれる形式がどんなふうに変わってきているか、ということについて少しずつですが、いろんな方と一緒に共同研究を行っています。何年か先に、面白い知見が得られると思っています。
いくつか挙げましたが、基本的に一番関心があるのは、メディアを媒介にした私たちの社会的コミュニケーションの在り方、言葉の在り方を含め、どのように変化してきているのか、それが私たちの感情や意識そして欲望にどう関連しているか、ということに関心を持って研究をつづけている。そうした多角的に考えることが必要なテーマを、学生と一緒に議論し、本を読んだり、調査したりしています。
若林:
私の専門は社会学です。社会学という学問は、何をやっている学問なのかよくわからないという人がいる一方で、社会科学の他の分野よりももしかしたら分かりやすそうと思っている人もいるかもしれません。ここまでみなさんが政治学、経済学、メディア研究について話してくれましたが、「政治」、「経済」、「メディア」がそれぞれ社会の一部であり、政治学、経済学、メディア研究がそうした社会の諸分野を対象とした学問だというのは、わかりやすいと思うんです。でも、それと同じように社会学について考えようとすると、なんだか違う感覚がある。私が学生によく説明する言い方をすると、「政治学、経済学、メディア研究、社会学」と並べるのは「チワワ、シェパード、秋田犬、犬」っていうような感じなんですね(笑)。社会学は「犬」なんですよ。「政治」、「経済」、「メディア」は「チワワ」、「シェパード」、「秋田犬」のように領域が特定化されてるんだけれど、「社会」というのは領域が特定されなくて、それを対象とするという社会学もぼわんと広くてよくわからない感じだとおもうんです。
それでは私が何をやってきたかというと、今まで研究の軸にしてきたのは都市の研究で、現代都市を対象とする都市空間と社会の関係の研究や都市の比較社会学的な研究、未来都市論や郊外論などをしてきましたが、その他に地図についてメディア論的に考えたり、やはりメディア論の視点から電話のコミュニケーションを研究したり、夏目漱石のテキストを使って、日本人が近代といかに遭遇したかを考えたり、ショッピングモールの研究をしたり、未来という時制は人間にとって何なのかを考えたりしてきました。
こんな風にお話すると、社会学って何を対象とするどんな学問なのか、ますますわからないという印象をもたれるかもしれませんね。でも、このように雑多に見える仕事も、私にとっては一つの大きな問題意識の下にあります。それは、人が他者と共にある世界をどう秩序化していくのかということです。ここで言う他者には人間の他者だけでなく、自然やそこに暮らす他の生物たち、イマジネーションのなかで考える神や霊なども含まれます。私がこれまでやってきたことは、このことを考えるためでの様々なアプローチだったとのだと思っています。
公共性や市民との関係で言うと、これまで研究の軸においてきた都市は、他者と共に世界を作るあり方の、人類が長い歴史の中で作ってきた一つの基本的な形態です。歴史上様々な形で存在してきた都市は、人間の歴史の中で公共性と市民というものをどう編成するかという課題に対する様々な解だったと思うのです。そこには古典的な市民社会モデルの原型となる西欧的な解もあるけれど、西欧的なものとは違う日本的な社会における公共的なものや市民的なものもあるし、現代社会における公共的なものや市民的なものをめぐる問題もそこから見えてきます。公共市民学専修でも、そうした視点からの授業ができたらと思っています。

公共市民学とは何か?
若林:
さて、一通り先生方の専門や、新しい専修への想いについてお話し頂きましたが、ここからは公共と市民、それから公共市民学という言葉をキーワードにそれぞれの視点や研究、考えをクロスオーヴァーさせていきましょう。
「公共市民学専修」という言葉を聞いたときに、何それって思う人が大多数だと思うんです。これまでの「社会科学専修」や、この言葉に含まれる「社会科学」も、受験生にはかなり漠然としたイメージだったと思いますが、公共市民学となるとますますわからなくなるかもしれない。そこで、公共や公共性、市民とは何か。私たちの社会を理解しようとするときに、それらの概念・視点がどんな意味を持つとお考えになっているかを、お聞きしたいと思います。
ごく普通に考えると、政治思想史は公共と市民とすごく関係がありそうな感じがしますね。メディア研究も、メディアはパブリック・リレーションやパブリック・オピニオンといったことと関係する、公共性や市民社会と深く関係した研究領域だというのが、直感的にもわかりやすいと思います。それに対して経済学、とくに近代経済学というのは、自由な主体であるホモ・エコノミクスとしての人間が、みずからの利潤動機の下に市場で自己利益の最大化をめざして行動するというのが、理論的な前提ですよね。先ほど黒田先生がおっしゃった制度の問題とか、メディアの問題とももちろんあると思うのですが、一見すると公共や市民ということから一番隔たりがありそうに見える経済学の方から、まずお話しいただけないでしょうか。
黒田:
難しいお題ですね。先ほど千野先生からどうやったら幸福になれるのかというようなキーワードがでてきましたが、私は経済学は幸福について考える学問だと思っていて、もう少し言うと社会科学全般は、人間ってどうやったら幸せになれるのかを考える学問領域なのではないかと考えています。先ほど若林先生がおっしゃった市場原理についてですが、確かに経済学では、市場原理に任せておくのがいいという発想が基本的な考え方として確立しています。ですが、市場は万全ではない、市場に任せておくと時に良くないことも起こりうるということも認めていて、それを経済学では「市場の失敗」といいます。そのような失敗があるということを認めて、それを是正するために、政府があり、政府が公共政策を実施したり、法律を作ったりすることによって、世の中をより良くすることができるという分野の経済学も発展してきています。例えば、市場原理に任せてみんなが周りのことを考えずどんどん生産してしまうと、大気汚染や水質汚染などの公害が発生し、社会にとって良くないことが起きてしまうわけですが、環境経済学という分野ではこうした市場の失敗をどう是正するかということを考えています。
このように経済学の中でも多様な広がりがあるわけですが、私自身は、これからは一つの学問を学ぶだけでは十分ではない時代になってきていると考えています。どの学問もそうですが、これまでの科学は、一つ一つの学問が、専門分野を深掘りするということで発展してきたといえます。それによってこれまでたくさんの発見があったわけですが、一方でそのために、たこつぼ化も進行していて、お隣の分野の研究者が実は自分とすごく似た問題意識で別の角度からおもしろい研究しているにもかかわらず、それを知ろうとしない。そうしたことがどこの分野でも起きているために、いわば科学においても市場の失敗が起きているのではないかと感じています。その意味では色々な分野の専門家が様々な角度から人間の幸福について考えているという、この公共市民学専修は、根底にある問題意識は共通しているけれど、ディシプリンや物事の見方の違いがあることをお互いに理解し、そこから新たな発想が生まれる可能性に満ちていて、とても面白い場なのでないかと考えています。
千野:
伊藤先生と黒田先生がジョイントでゼミを最近やられたと伺いましたが、どのようなテーマを扱われたのですか?
伊藤:
フェイクニュースに関して、経済学のゼミとメディア学のゼミですが、黒田先生のゼミの学生と私のゼミの学生が、10グループぐらいに分かれて議論を行いました。私たちから見ても成功だったと思うし、学生にとっても刺激になるいい経験だった。経済学の用語で話が出たり、メディアの用語で説明が出たり、それでも一つのテーマについてお互いに話ができて、いろんな見方ができることが理解できたという点で、短時間でしたがとても良かったと思います。
今の黒田先生の話を聞いて、多様性、多様な視点ということで話が出た。「公共」ということを考えるときにも、それがキーワードだと思います。ぜひ新しい専修に入ってきてくれる学生に、「言葉を大事に」学んでほしいと思います。「公共」って手あかがついているけれども、その言葉をめぐっていろんな意見があるし、そうしたいろんな意見を自分なりに考えていく、ということがとても重要なことだと思うからです。曖昧である、いろんな意味を内包している、だからこそ、手あかのついた言葉の「手垢」の部分を自分なりに削ぎ落として、自分の言葉として受け止めて、考えていくということですね。「市民」という言葉もそうだと思うけれども、言葉を大事にする、言葉を自分のものにして考えていく、そのようなことができる専修にしていきたいですね。それが私の希望ですし、期待です。
もう一つ指摘したいのは、先ほど若林先生が「他者」という言い方をしたが、これも決定的に重要なことがらだ、と考えています。自然もそうだし、面と向かっているまさに他者も、「他者」です。私たちが「他者」とどう対話ができるか。アーレントはポリスについて考察したけれども、見知らぬ、言葉も考え方も違う「他者」と出会い、対面した時に、どうわれわれは対応するでしょうか。そのとき、「怖い」かもしれないし、「恐れ」の感情を抱くかもしれない。不安に駆られるかもしれない。逆に、この人ってなんかすごい力をもっていると感じるかもしれない。そのすごさが、或る種、自己を圧倒するような「暴力的なもの」として感じるかもしれない。そこにこそ初めて、「公共」ということがらが生まれるというのが、アーレントの一番言いたかったことなのだろうと、私は思っているのですね。これから、社会のなかで、「他者」と出会い、それにどう向き合うか、それが「公共市民」というコンセプトで何かを考えていくことの「原基」にあることがらだと考えています。
その点で、千野さんの言われたことですが、私がとても大事だなと思ったのは、「社会」というか、ソーシャルな領域でけでなく、実はプライベートな領域も「他者」と向き合う、つまり「公共」と出会う場なのだということです。いつも、パブリック=公共というと、社会のなかのパブリックな領域だと考えがちになるのですが・・・。例えば、妻と向き合っていても、一瞬「他者」になる時があるわけで・・・。
若林:
いや、一瞬じゃないと思う(笑)。常に他者(笑)。
一同:
(笑)

伊藤:
繰り返しますが、「公共」というと、すごく固いイメージがついてまわり、社会的な領域のことだと考えてしまう。でも、先ほど述べましたが、プライベートな領域だって、よく理解していると思っている子供や妻も、実は全く理解できていない「他者」として、不思議な存在として浮かび上がってくることがある。いつもそうだと大変なのですが・・・。つまり、その時に、どうやって関係を編み直していくのか、そこでどうルールを作っていくのか、ということが大事になるわけです。プライベートな領域でさえというか、プライベートな領域だからこそというか、そうした日々の営みがある。ましてや、現代の社会は、従来の方法や思考では対応できない課題が山積しているわけです。そのときに、異質な「他者」と出会うこと、その「原基」的な位相から「公共」を捉えるという感覚で、社会を見つめて考えることがすごく重要になっている。
そういう意味で「公共市民」という、手あかのついた二つの言葉を、もう一度、垢を取り除いて再生し、社会を考えていくキーワードにしていきたいですね。
「公共性」とは何か?
若林:
今、伊藤先生がアーレントとおっしゃいましたが、ハンナ・アーレントといのは、ドイツ生まれのアメリカの政治思想史家・哲学者ですね。アーレントが社会を考えるときは、まず基本的な人間の活動の二つの領域として私的な領域と公的な領域を考えます。つまりプライベートprivateとパブリックpublicという領域がまずあって、ソーシャルというのはそれらに遅れて歴史の途中から出てきます。これが社会学的にはすごく重要なことだと思うのです。プライベートとパブリックというのは古典古代のポリス的なものです。ポリスではまず貴族や市民が奴隷を使って生活の必要を充足する私的な経済=家政の領域であるオイコスがあります。経済学の元々の語源はオイコノミアで、オイコスの学ということですね。パブリックな世界というのは、そういう必要を充足する私的な場所としての家政の領域から人々が自由になって、言論、コミュニケーション、芸術を行う領域で、それが古典古代的な意味での都市だというのがアーレントの考え方です。
しかしこのモデルは現代社会を考えるうえでは単純すぎる。なぜなら、これら二領域とは異なる領域として、近代になるとソーシャルなものが現れるからです。それは、プライベートな領域に囲い込まれていた必要性のための労働が、これまで必要性のための労働とは無縁だったパブリックな領域にはみ出していき、人間集団の全体を構成する領域になってくる。そうしたソーシャルな領域、つまり近代的な意味での「社会」がポジティヴな現実性をもって現れてくる時に、自分たちの社会をどうとらえるかという問題意識の下に、近代の社会科学は始まったのですね。
公共市民学という私たちがこれから始めるプロジェクトが、そうした社会のあり方とどう関わっていくのかが重要だと思います。私的なもの、社会的なもの、公共的なものとの関りを、私たちが現代の社会においてどう考えていくことができるのかという問題です。そこで出て来る問いの一つが、現代において「市民」という主体とは何なのかということです。
伊藤先生がおっしゃるように、「公共」も「市民」もある意味ですごく手あかがついていて、その言葉が持っている可能性が見えにくくなっていることがあります。日本で「公共」というと、すごく単純に、お上とか天下とか公みたいなものに収斂していってしまうこともある。それから、市民というと、いやな言葉だけど「プロ市民」という言葉がありますね。昔、東京都の某区のNPOの活用のための制度作りのワーキンググループのようなものに参加したことがあったのですが、そのとき驚いたのが、お役所の人が「市民」という言葉を使いたがらないということです。彼らにとって「市民」というのは”うるさい人たち”のことなんですね。「市民」というのは現代の日本では、そういう形で矮小化されてしまう概念でもあります。
こんなこともありました。前任校の講義で市民と都市と市民社会について話をしていた時、受講していた学生のひとりから、「先生の言う『市民』というのは村民や町民とどう違うんですか」と質問されたんです。この時、あぁなるほどなぁ、と思いましたね。市民社会の「市民」とはヨーロッパの都市の「市民」がプロタイプで、近代的な意味での市民は、それが公共空間の中で普遍化していくときに現れてくるものですが、「市民」についてのそういう感覚は、私たちの社会ではうまく根付いていないように思います。
そんな日本的な文脈で往々にして陥りやすいのは、「社会」を「公共」に還元してしまったり、「私的なもの」を「公共的なもの」に還元してしまったりすることです。「公共」という概念で表せるものと、「社会的なもの」や「私的なもの」との間の緊張関係が、現実に生きられる社会にはあります。私的な領域と公共的な領域との緊張関係、あるいは私的なものと社会的なものとのあいだの防波堤としての「公共」――ハーバーマスはそのように考えるのですが――が内包する緊張関係を、それぞれの学問のディシプリンから、そしてまた学問相互の関係を意識しながら考えていくことが、公共市民学という試みでは重要になるのではないでしょう。
このことについて、千野先生はどうお考えですか。
千野:
日本のいわゆる「市民社会論」が近代的な発展モデル、要するに西欧の社会を理想化するモデルを前提にする流れはあって、そういう意味で伊藤先生がおっしゃったように手あかがついた概念という側面があると思います。
日本思想史家の前田勉さんの『江戸の読書会』(平凡社)というご著書で、「会読」という儒学の文化のなかで、江戸時代は、上下の身分が強く固定した社会のなか、身分を離れて読書会のなかでは輪になって対等に議論して、先生が学生たちの話を聞き、最後に講評するというシステムがありました。もちろん前田さんはハーバーマスを意識してお書きだとは思いますが、日本にもそういう空間が成立していた。そういう意味で西欧的な概念へのある種のコンプレックスを持って、日本に市民社会がなかったから戦前戦中の様々な破局が起きたので、国家に対抗する強固な市民社会を作らないと、といういわゆる市民社会派的な発想と少し距離をとったところで、市民社会や公共性のあり方というのを考える時期に来ていると思います。それは現在の政治理論における公共性論がもはや欠如モデルでないことからも明らかだと思います。こうした作業は、その「手あかのついた概念」を地に足についた形でわれわれが手にすることになるのではないでしょうか。
あるいは丸山眞男も議論していますが、例えば明六社や交詢社など、明治の初期にはヴォランタリーな団体や結社が様々に存在していて、そこでは身分や出自などの社会的な背景から離れて議論する場がありました。ただ明治10年くらいになると、警察システムなどができてつぶされてしまった。こうした自発的結社の経験が理想化された西欧のもので、日本にはないという図式が事実と異なっていることはもう少し強調されるべきだと思います。
若林:
俳諧もそういうのに近いですね。俳句というメディアを通じて身分を超えて人々が交流するようなサークルみたいなものがありました。近世日本の数学である和算の世界でもあったようですね。和算愛好家が各地にいて、難しい問題を出したり、それに対する解答を出したりということでコミュニケーションしあっていたらしい。そうした日本的な公共的コミュニケーションは、近代にも流れ込んできています。例えば夏目漱石は、職業作家になる前に親友の正岡子規が主宰する『ホトトギス』に写生文を書いていた。『吾輩は猫である』も『坊ちゃん』もそこから生まれました。今日の俳句や短歌の結社につながっていくそうしたシステムは、文芸的公共性の空間を生み出します。その後も文学青年や思想青年たちは、自分たちで雑誌を作り、その誌上で交流しつつ、それをより広い読書界という公共圏へと開いていきました。芥川龍之介も太宰治も、宮沢賢治もそうでした。こうした青年たちにとって雑誌というメディアが可能にするコミュニケーションの空間は、今の若い人たちにとってのSNSのような新しさをもつものだったと思うのです。「公共」という概念からは、そんなことも見えてきますね。
千野:
先ほど伊藤先生がおっしゃったことですが、「公共圏」と「公共性」というのは違いますね。公共圏ではない私的な空間のなかにも公共性はあり得ます。つまり、家族やパートナー相手の私的関係のなかにも、理由を挙げることで、相手と納得し合あいながら物事を決めていくことは良くあるのではないでしょうか。例えば、旅行の行き先であるとか、家事の分担であるとか…しかし「公共圏」といってしまうと、空間的なイメージ回収されてしまいがちだと思います。ドイツ語のÖffentlichkeit(=公共性、公共圏どちらとも訳される)をどう訳すかという問題は日本語だけでなくて、英語でもあるのですが…
若林:
あの概念自体には、そもそもは空間的な意味はないですよね。
伊藤:
Öffentlichkeitは「公共性」と訳されていますが、日本語で思考しているわれわれにとっては感覚的に理解しにくい言葉です。ただ、ドイツ語圏に行ってみると、日常的に使われている言葉で、たとえば会議をやっていると、その入り口にビラが貼ってあって、Öffentlichと書いてある。それは、「誰でも入っていいですよ」という意味なんですね。それがもともとの意味なんです。空間概念ではなく、関係性にかかわる概念でしょう。
若林先生がおっしゃった村民や町民と市民がどう違うかという点はとても考えなければならないことです。僕たちは、普段、家庭を持てば、夫であるとか妻であるとか、役割を担って発言したりしてるわけだし、町民として、村民として、あるいは会社に行けば社員として、部長、専務として、もっと大きい範囲で考えれば、日本国民としてとか、どこか役割を担って、属性を担って発言している。しかし、「市民」という概念は、役割を指しているわけだないし、地域や国家に所属していることを指すものではないでしょう。とても抽象的な言葉です。だから「社員として」という言葉は「どこそこの会社に所属している人間として」という実質的な意味をもっているわけですが、「市民として」という言葉を突き詰めていくと、「私」という個体性ないし単独性しか出てこない。「私」はどう思うか。「私」はどう行動するか、というその「私」です。
学生が、若い感覚で、この「市民」という言葉をどう考え、どう受け止めていくか、一緒に考えていきたいし、千野先生が先ほど指摘された、江戸期や明治期の憲法ができる過程の話ですが、いろいろな読書会があったはずです。その時も、村民としてではなく、夫としてではなく、「私」として参加したはずです。そうした空間や場は面々として続いているし、そのように役割に捕らわれた社会とは異なる、「私」の自己表出のその時代ごとのかたちや強度が、いまどこに、どのように生まれているのか、あるいはそれをどう作り上げていくのかということを含めて、ぜひ学生と議論したい。

公共市民学専修で学ぶことの意味
若林:
そうした「公共」や「市民」という問題を大学で具体的に教えていくときに、どのようにしたらいいとお考えでしょうか。あるいは、そうした切り口から社会について学んでいくことが、これから大学に入って勉強する人たちにどのような意味を持つのでしょうか。
私は、大学自体がある種の公共的な空間だと思うんです。大学という場所は、いわゆる「実社会」から自由になって人と人とが違いに他者として現れあって、出会うことを保証する空間だと思うのです。互いに他者として現れるとき、他者から見られることによって自分を発見する契機が生まれます。アーレントも言っていますが、自分が何者であるかは結局他人にしかわからない。他の人びとへの現れのなかで自分というのを発見しながら、他者と共に世界を作っていくのがパブリックな空間なのだと思います。ゼミも授業も、あるいは大学という場所自体がそういう場所なのではないでしょうか。そういう場所としての大学で、どういうことを我々は学生に伝えていけるのかということについては、どうお考えですか。
黒田:
先ほど伊藤先生が「私」をどう自己表出するかということをおっしゃっていましたが、私は幼少時代アメリカで育った経験がありまして、そこでは、常にあなたはどうしたいのか、あなたはどう思うかということを問われる環境でした。子どもでも、私はこうしたい、なぜなら自分はこう考えるからだ、ということを言わなくてはならない。そうしたスピリットが割と私の元来の性格と合っていたのか、すんなり受け入れることができていたのですが、日本に帰国したら、他者との距離感というものを非常に気にしなくてはならない、そういう文化の違いを痛切に感じたことがありました。
若林:
「みんながこうするからこうしなさい」というやつですね。「あなた」じゃなくて「みんな」(笑)
黒田:
はい(笑)。その文化のギャップが子どもの時は苦しくて、自分のアイデンティティをどういう風に形成していくかを悩んだ時期もありました。その過程で顕著に感じたのは、日本では創造性や独創性が大事だと小さい頃からずっと教えられているにもかかわらず、とびぬけた発想や異端な意見をいうと疎まれる、そうしたダブルスタンダードのなかで我々は教育を受けているのではないか、という点です。そうした教育システムのなかで、学生たちは模範解答を導き出すことが良いことだというスタイルで勉強をしながら大学に入り、社会に出る一歩手前になって突然、あなたのオリジナリティは何、ということを求められる。そうした画一的な正解を良しとする教育と、一方で創造性や独創性が求められる社会というギャップを日本の大学はゼミで埋めているのかなという気がしています。公共市民学専修におけるゼミの役割は、解は一つとは限らず、世の中には色々な考え方があり、解決されてない問題もまだまだたくさんあって、それをどのように新しい発想で解決していくのかを考える場ではないかと考えています。
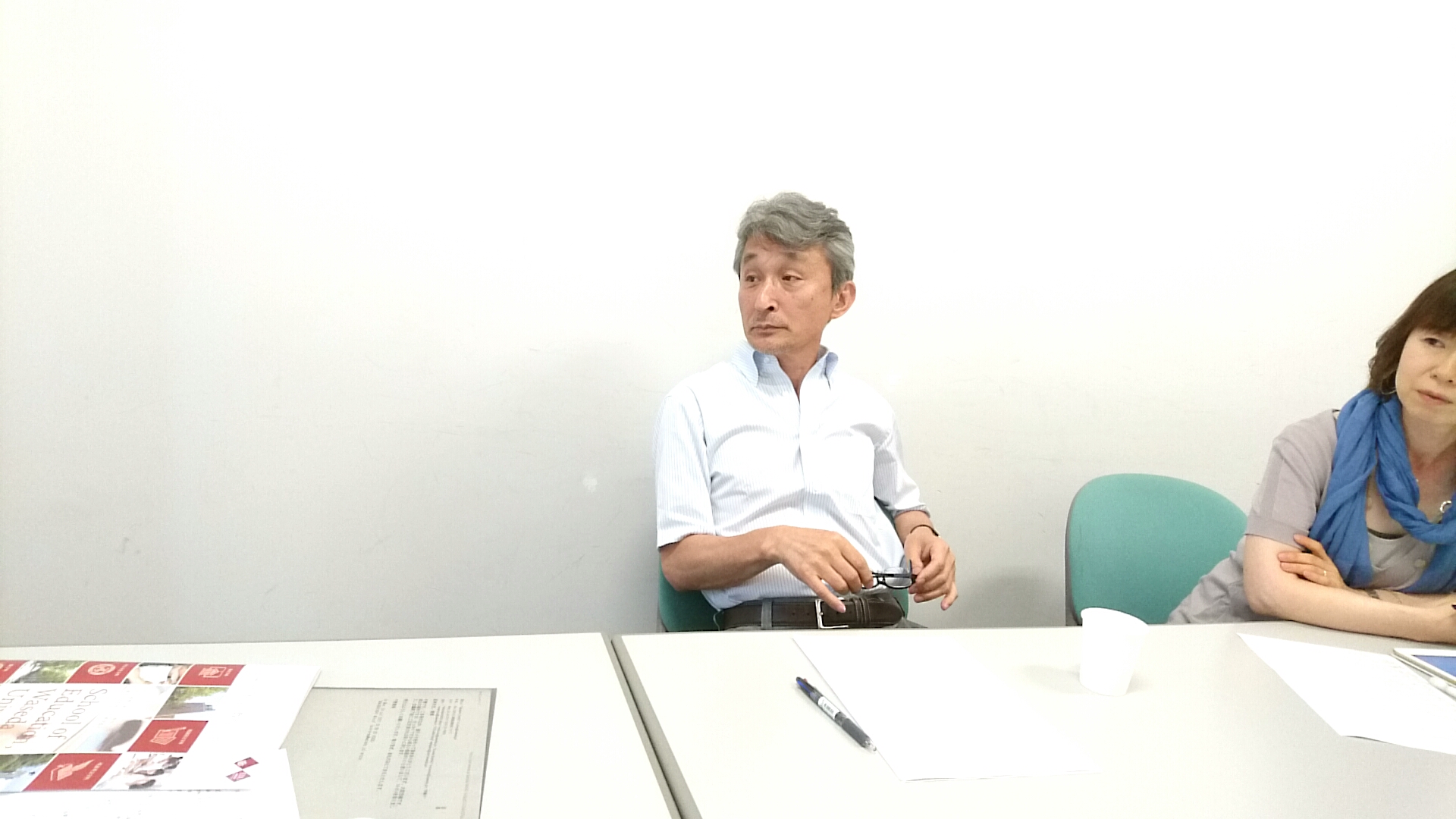
若林:
公共市民学という学問自体がいまはまだひとつの試みとしてあって、現実にはいまだ存在しないということにも関係することですが、学問というは「これが完成した学問で、これを一通り勉強すればその学問をマスターできます」といったパッケージとしてあるわけではない。多くの大学生やこれから大学に入ろうと思っている人は、そんなパッケージされた完成品として学問があって、それを教えてもらおう思っているかもしれないけれど、学問というのは決して完成することのないコミュニケーションのプロセスとして存在するのです。どんな教科書も定説も、現時点でとりあえず正しいとされていることを誰かが発信しているのであって、学問を学ぶというのは、まずはそれを受け取ることです。そして、その受け取ったものを自分なりに吟味し、検討し、応用し、批判して、自分なりに応答していくのが学問する、研究するということですね。研究者というのはそうした学問的コミュニケーションを仕事にしている人です。私がゼミや講義でいつも思うのは、学問がそうしたコミュニケーションのプロセスであるということを理解してほしい、ということです。特にゼミは、みんなで話していくことによって、考えるべきこと、問うべきことを発見していくのですから、あらかじめ「正しい答え」が分かっていたら議論にならない。分からないことをもってきて、みんながそれを共有して、考えるべきこと、問うべきことと、さしあたってその答えになるかもしれないことを発見していく。これは市民社会で世論形成していく原理と一緒なのだと思うんです。「これがわかれば全部解決」というような最終的な解決策は見つからない。たとえば現代のドイツで「最終的解決」というと、ものすごく悪いイメージですよね(笑)。「最終的解決」というのはナチスの時代のホロコーストのことじゃないですか。社会というのはよりよい答えを他者たちと共に探していくプロセスなのだから、それを終わりにするような最終的な解決を求めてはいけない。そういうプロセスとしての社会というものに、他者たちと共に付き合っていく。その付き合い方の作法がとても大切だと思うのです。そうした作法を、大学に居る、授業を聞く、先生・仲間と話す、論文書く、といったプロセスのなかで身に着けていくことができるのではないかと思います。
千野:
私は非常に教歴が短いですが、びっくりするのは、学生は本当にいろいろな可能性、あるいは未完成や未熟なところを多様にもっていることです。授業をしていて、ある話し方をしても、まるで反応しなかった学生が、別のアプローチをすると、見違えるような反応をすることが何度かありました。私自身にも、恐らくその学生にも、何か琴線に触れたのかは分かっていないのだと思います。こうした授業のimprovisationalな側面には、授業をやる方も多くのことを気づかされる、面白い経験です。私も学生と付き合うことを通じて、自分自身が新たな他者性に開かれているし、逆もそうあってほしいと授業をしているなかで日々感じています。
学生と話していても、高校までは同質的な社会のなかで生きてきた人が多いのだなと感じます。そんななか、早稲田大学のような大学に来ると、多様な経験や様々なバックグラウンドをもった人と出会うことで、自分自身の視野が広がるのだと思います。早稲田だけではありませんが、そうした多様性が大学において縮小化してしまうのは非常にもったいないことです。それぞれのバックグラウンドや出身地域などの属性を超えて、様々な人が出会い、共に同じ教室で学び、サークルなどでお互いが何をしているかを知り、そうした経験を通じて自分自身が何をしているか、何をするべきかを発見する、そういったプロセスにもう少し身を投じる人が増えて欲しいと思っています。
伊藤:
僕はゼミに関しては、ほぼ若林先生と同じ考え方でやってきた。ゼミを個別指導中心にやられる方もいるが、僕は一貫して15人いたら15人がとりあえず何かをしゃべり、そこで全然自分と違うことを発言しているとか、この本をこんな風に読むのかといった発見が一番大事だと思う。そうすると解答はたぶん一つではなくて、自分の考えに改めて気づかせてくれる、そういう発見がゼミでは必要だし、それは大学の基本だと思う。ただ、この間、とても残念に思うのは、他者の話は聞くが、本に関して言うと、本と対話するという経験はいまの学生にとっては結構難しいということです。本の内容を整理してレジュメを用意して報告することはできるが、それ以上に、この本から僕は、というのがすごく弱くなってきている。一つ一つの言葉から受けるイメージや肌触りを感受することが結構難しくなっているという印象です。
早稲田に来てから数年間は2コマ連続でゼミをやっていた。本を読ませて、理解できずに詰まっても、15分沈黙が続いても、辛抱強く、誰かが話し出すまで待っていたんです。誰もしゃべらない時間でも大事だと思っていた。とりあえず本に向き合え、という風に。それで2コマ、3時間やっていました。しかし、だんだんこっちもきつくなってきて(笑)、5分空白があるだけで、ちょっと何か言わないとだめだなとか(笑)、というふうになり、2コマ連続もだんだんきつくなってきたという感じがしています。
それでも、やはり学生が、一つ一つの言葉と向き合って、さきほども言いましたが、そこで学生が本と対話する、専門書と対話するという経験を、ますます鍛えていく必要があるなと強く感じている。
それからもう一つ、これまで社会科学専修の学生は、外に出る機会がすくなかったような気がします。もう少し大学以外のところに出かけていって、そこでいろんな人たちと出会い、いろんな経験するという機会を増やしたいですね。新しいカリキュラムでは実習系の科目を多くしたので、そこで学生が他者と向き合うということを身をもって体験できるように進めたいと思っています。
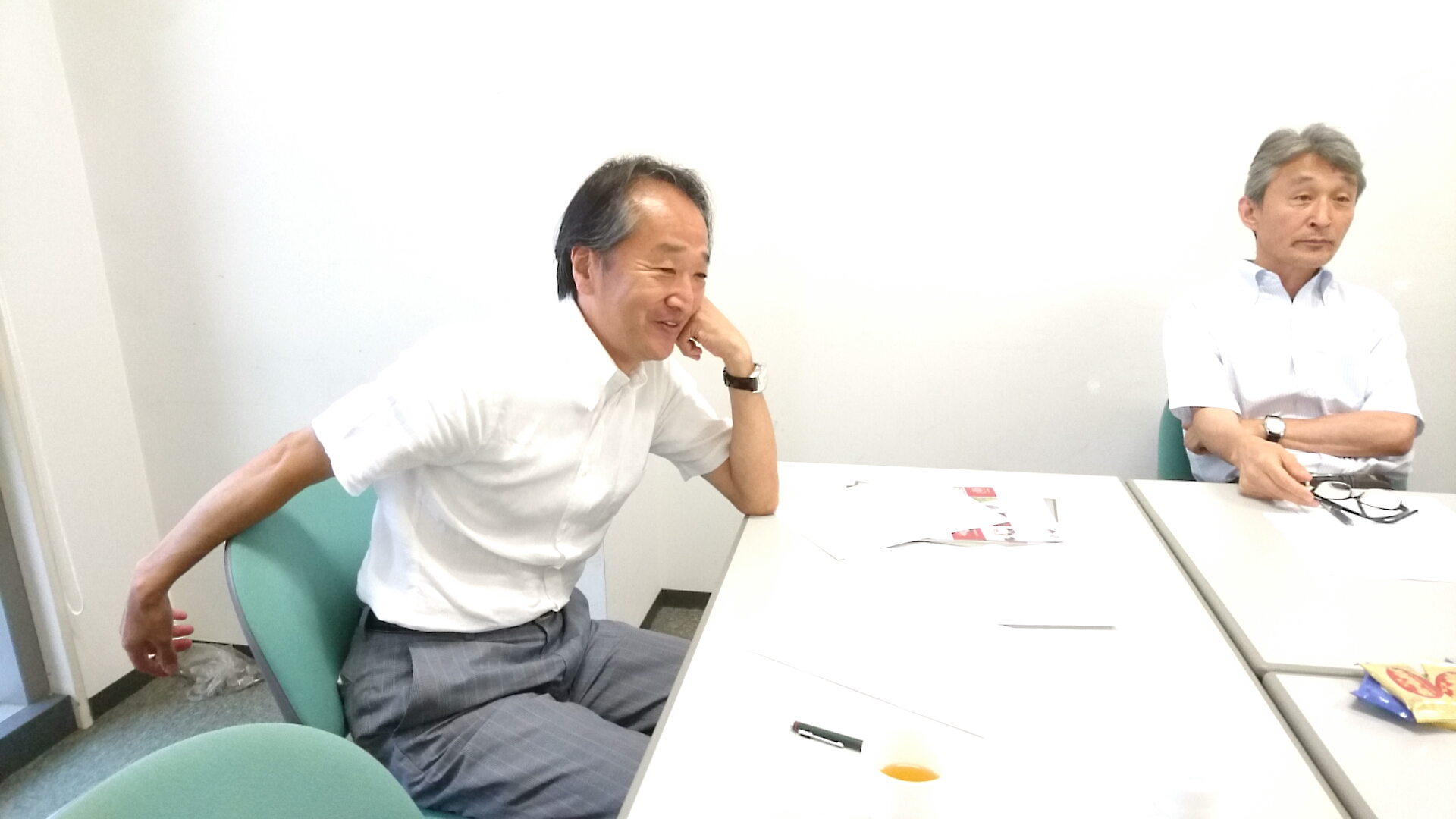
若林:
黒田先生のところはグループワークをしたり、外から人を招かれたりされてましたよね。
黒田:
はい。一学年だけでなく上下の学年混合のグループワークをしたり、起業をしている方や国会議員など様々なジャンルで活躍している方を招いて講演をしていただいたり、他大学との交流も図ったりなど、様々な活動をしています。同じ専修のなかですと、先ほど伊藤先生のゼミとインゼミを行ったというお話がでましたが、一昨年は遠藤美奈先生の法律のゼミとイベントを開催し、腎臓売買の是非について議論をしました。経済学では、腎臓は二つ持っているわけだから、売買が可能になったら提供する人も増えて、人工透析などで苦しんでいる人を救うことが可能になるのではないか、という発想があります。ところが、法学サイドでは臓器の売買を認めるのは良くないのではないかという発想があり、議論が白熱して時間が足りないくらいでした。最後には、これだけ異なる角度からの考え方が存在するのだということを参加した学生が実感できたイベントになったと思います。こうしたエピソードからも、いろんな人と交わるというのはすごく大切だと思いますし、学生という閉じた社会にこもるのではなく、どこかに出かけていったり、誰かを招いたりといった機会も重要で、ゼミではそうした場を増やしていきたいと思っています。
千野:
これだけ社会科学の様々な分野の先生方が、しかもそれぞれのご研究では第一線でやってらっしゃる方が、こんなに集まっているところはそんなにないのではないかと思っています。私自身も、公共市民学専修や広く社会科の先生方のご本やご論文から勉強させて頂いてきました。例えば、近藤孝弘先生の『国際歴史教科書対話』(中公新書、1998年)は私が高校三年生の時に読みました。ちょうど歴史認識における修正主義が擡頭してきた頃でした。私にとっては懐かしい本であり、また歴史学や社会科学が何をしているのかについて理解をもつきっかけのひとつだったと思います。そうした教員が多くいるのだから、学生にももうちょっと教員から得られるものを自分自身で引き出すとか、その、教員をその気にさせるというか、教員を使うというか(笑)、そういう努力をしてほしいですね。
教員が学生に期待すること・学生が大学でできること
若林:
大学の使い方だと思うんですね。もっと大学を上手に使ってほしい。登録した授業をおとなしく聞いているけれども、それを超えて何かおもしろそうな先生のところに探検しに行ったりといったことをもっとしてもいいのにな、と思いますね。自分のゼミの学生でも、毎週ゼミの時に会う時だけで、結局研究室には卒論の時に一回ぐらい来たかな、みたいな、そういう人がいたりするじゃないですか。そういうのはもったいないと思うんです。
ところで今日集まった4人は、全員が早稲田大学出身ではないですよね。千野先生は大学院は早稲田ですが、他の3人は他の大学・大学院の出身者です。みなさん、自分たちの大学・学生時代と比べて、今の大学や学生についてどう思われますか。
伊藤:
これは後で消してくれることを前提で言いますが・・・(笑)。卒業の時点で自分が学んだ分野やテーマについて、4割から5割はしっかり勉強した、勉強できたという実感をもってほしいと思うし、それより少し下ぐらいでもいいかなとも思う。なぜそんなことを言うのかと言うと、その分野を90パーセント理解できたという人はめったにいないと思うけれども、一方で理解できたのは1割から2割だったということでは教える側としてはちょっとつらいし、困っちゃうわけです。
でも、半分くらいしか理解できなかったという思いが残るにしても、大学という場や空間は特別なところだった、という気持ちはもって欲しい。社会に出てから、大学ってあんなもんだった、というのではなくて、大学ってやっぱり違う場所だ、できれば大事な場所だ、と思って卒業してほしい。
それがないと、そうした人が増えないと、大学は社会の中に飲み込まれてしまう。若林先生が言われた、ソーシャルな論理のなかに、ある種パブリックが、大学すらもが飲み込まれてしまい、それを多くの人が支持してしまうようなことになったらもうおしまいだと思っている。そういう意味で、大学って難しかった、半分しか分からなかった、けれどもよい意味で大学は別の空間だった、という感覚も大事にしていってもらいたい。これは後で消してくれていいけど(笑)。
黒田:
大学って難しいところだった、という感想は私自身の学生時代を振り返っても共感するところです。大学に入って一体どんな新しいことを勉強できるのだろうと思って入学して講義を受けたら、分かりやすく話をしてくれる先生がほとんどいなくて、少しがっかりしたことを記憶しています。振り返ると、当時は高校を卒業したばかりで、お客さん意識のような受け身の発想が強く、大学に入ったらきっとすごく面白い先生が楽しく講義をしてくれるに違いないという期待があったのだと思います。
いま「入門社会科学」という1年生の授業を受け持っていて、学生と接していると当時の自分をそのまま映しているかのように感じることがあります。入学当初は目が輝いているのに、数週間たったら、「大学の授業って難しくて面白くない、バイトやサークルをしていたほうずっと楽しい」、そんな悩みを学生から聞くこともあります。そこで考え方を切り替える為に私が毎年言っていることは、大学の先生になるのに教員免許はいらない。大学の教員は科学者の一人で、最先端の科学を追及していて、講義は科学としてこれまで解明されてきたことはどんなことで、どれだけのことがまだ解明されていないのか、そうしたことのほんの一部を教えてもらうような場だから、講義だけ受身で聞いていたら得るものはほとんどない。先生に食らいついていって、自分でもっと学びたいことがあるのだけれどもどういう本を読めばいいだろうかと相談したりなど、自分から学び取っていくという姿勢になって初めて大学の面白さというのが出てくる、そういうことを話すようにしています。大学で学ぶ中で、何遍読んでも分からないというような本に挑戦する経験も良いと思いますし、自分なりに頑張って分析してみたけれどももっとすごい発想で分析している論文をみつけて科学の奥深さを感じたりなど、そういった様々なトライアンドエラーの経験を通じて科学ってこういうものなんだということが少しでも分かる場であってほしいと思っています。

千野:
伊藤先生と黒田先生がおっしゃったことは、自分の経験からしか見ないと分からないことが多くあって、しかしそうした経験外でありながら学べることに、人間の人生にとって重要ことが多くあるのだということではないか思いました。自分の人生で経験したことからしか考えられない、話せないという発想でいると、様々な考え方にも触れることができないですし、それでは大きな知的成長や人格的発展は望めないと思います。先ほど伊藤先生が「本と対話する」ということをおっしゃっていたけれども、人間の人生はとても限られた時間と空間のなかにしかないので、本を読むことはそうした限界を飛び越えさせてくれることですよね。そういうのを通じて自分の狭い経験の世界だけでものを考えるのではなくて、自分が経験できないような世界になることに飛び出していってほしいし、そうした知的成長のきっかけはやはり大学のなかで得られるのではないかと思います。人生には正しい答えのないことがたくさんありますから、強いられた選択肢の中でベターなものを探していくということが大半だと思います。そこで自分の経験してきたことだけに頼ってみても、自分を客観的に見て良い選択肢を選び出すということは難しいでしょう。こうした難しい時に参照軸になるのは、自分の経験したわけではないけれども、本を読んだり人を見たり話を聞いたりして学んだ、様々な考え方や先人の選択や人生だと思います。社会環境のなかに自分が埋め込まれているということをまず知ること、それと同時に、だからといってより良い選択肢が開かれていないわけでもないことが見えてくるのではないでしょうか。学生には自分の経験からだけ物事を考えたり判断したりするような狭い世界からは足を洗ってほしいというか、その経験の外で何か引っかかったことがあれば、黒田先生がおっしゃったようにそれに食いついていって、それをきっかけに経験主義的な狭い世界を抜けて、いろんな世界に開かれて行ってほしいです。そのひとつの大きな契機が大学での学問だと思います。
若林:
千野先生が経験を超えるという風におっしゃいました。それは半分正しいと思うのですが、もう半分ではやはり、経験というのも大切ですよね。伊藤先生や黒田先生がおっしゃったこともそういうことだと思うのですが、大学の4年間って、人生の中でもすごく特殊な時間じゃないですか。今の学生はアルバイトでよく働いていますが、いわゆる企業人としては働くことからは解放されているし、小中高までのような勉強からも解放されてもっと自由に勉強することができるし、サークルであるとか、旅行であるとか、ボランティアであるとか、様々な経験をすることもできる。そうした経験をちゃんと味わい、かつまた書物や議論を通じて経験を越えた世界の見方も知っていくというのが大切だと思うんです。
早稲田大学に来て思ったのは、早稲田大学って幸せな大学だなぁ、ということです。学生がすごく楽しそうでしょ(笑)。学生の多くが早稲田を愛してる。学生以外でも、卒業生はもちろん、そうでない人たちでも早稲田が好き、という人がたくさんいますよね。でも、そんな幸せな大学で学生生活をおくっている学生たちの中で、学問がどのくらいのウエイトを占めてるんだろうって思ったときに、いやどうかなこれはと思ったりする(笑)。学問の環境としても素晴らしい大学だと思うのですが、全然それを使わないで、先ほど黒田先生もおっしゃったけれども、入学してひと月ぐらいで多くの学生が大学を見限っているように感じます。これは教師の責任も大きいですね。我々教員がもう少し学生を誘惑して、学問の面白さと楽しさと、難しいことの面白さを伝えていかなきゃいけない。
それから、学問することと、サークルで活動したり、映画を見たり、恋愛したり、世界旅行したりといった経験を、それぞれ無関係なものだとは思ってほしくないですね。例えば、先ほど黒田先生が経済学は実はお金のことだけではなくて、人間が生きていく中での心理とか生活とかすべて関わってくるということをおっしゃいました。仕事や企業活動をしていなくても、サークル活動や恋愛をしているときも、それらを通じて人は常に経済を生きているわけですよね。同じように、人は常に政治のなかにあるし、様々な社会関係のなかにある。メディアを通じてしか出会わないものもたくさんあります。人間が社会を生きていくそうしたあり方を、思う存分利害関係抜きに味わい、また考えられるのが、大学という場所の面白いところだと思うんです。その意味では大学の経験というのをしっかり味わってほしいのですが、その一方で経験だけに埋没せず、それを越える視点や考え方を身につけて欲しいですね。
学問というのは、一方では現実から舞い上がる翼みたいなところがありますが、さらに重要なことは、舞い上がり、そこから世界を見たことによって、再び地上に降りたときに歩き方や周囲の見え方が変わっているということです。そんな風に社会と世界の見方を変え、生き方を変えることができるかもしれない“知の扉の鍵”を与えるのが、社会科学を教える教師の仕事ではないかと思います。公共市民学という私たちの試みが、社会科学をそのようなものとして使う方向と可能性を示すものになったらいいですね。
今日はどうもありがとうございました。
座談会を終えて(伊藤守)
普段顔を合わせてはいるものの、講義やゼミそして校務や雑務に追われて、専門分野に関する議論や会話の時間すらとれない日常のなかで、1時間足らずとはいえ、この座談会は、大変愉快で、意義のある時間だったと感じました。「公共」も「市民」も、日常的に使われている言葉であり、一方で重要な専門的概念でもあります。その両極を行ったり来たりしながら、その奥行きを感受し、思考の補助線とすることで、現代社会を「複眼的」に見ることが可能なのでしょう。
お薦めの本
専門分野に入る前に「精神の生態学=エコロジー」を豊かにするための2冊の入門書を紹介します。
鷲田清一 『「聴く」ことの力――臨床哲学試論』ちくま学芸文庫
現象学を専門とする哲学者の本ですが、柔らかいタッチで描かれた本書は、「ふれる」「かたる」「きく」「まなざす」という多様なかかわりから生まれる「他者」と「自己」との関係を描いています。「公共」ということがらの「根本」を考えるうえでも重要なヒントを与えてくれます。
テッサ・モーリス・スズキ 『過去は死なない――メディア、記憶、歴史』岩波現代文庫
オーストラリア国立大学の歴史学、社会史、文化研究を専門とする研究者の本です。上記の本と比べると、歴史の視点が重視され、みなさんが自明のことと考えている東アジアの関係が問い直されています。「他国」と「自国」の「密かな交流」に目を向けると、これまでとは違う「他者」と「自己」に出会えるでしょう。
座談会を終えて(黒田祥子)
短い時間でしたが、とても楽しく、有意義なひとときでした。若林先生もおっしゃっていますが、この座談会のページをご覧になった方が、異なる分野の研究者の間で議論が展開していく、ジャズの即興演奏のようなライブ感やワクワク感を少しでも感じていただけたとしたら嬉しいです。
多くの問題が複雑に絡み合っている現代社会では、一つの専門分野に特化して学ぶだけでなく、異なる角度から物事を眺め、多様なアプローチがあることを知り、それを実際の問題に応用して解決していく力がこれまで以上に必要になってきています。ただし、他との異同を知り、その違いのおもしろさを理解できるには、まずはそれぞれの分野の基礎を学ぶ必要もあります。こうした考え方から、公共市民学専修では、「広く多くの分野を学べる」という考えではなく、その一歩先をいく発想でカリキュラムを組んでいます。
まず、1年生では、「公共市民学」という大きな傘の下で、複数の学問からどのように「公共」や「市民」を捉えることができるかを学び、そのうえで2年生までに、政治学・法学、社会学、メディア論、経済学のそれぞれ基礎を習得します。これは、いわば「楽譜の読み方」を勉強したうえで、それぞれの「楽器の奏で方」を学ぶ場と位置づけられます。基礎を習得した3年生以降は、学生の関心にあわせて、さらに学問を探求していくという場を設けていますが、これは自分の担当の楽器をもちつつ、多くの楽器とのインターラクションを楽しむ場と捉えることができるのではないかと思います。「公共市民学」という新しい枠組みの中で、自分に力をつけたいと考えている意欲のある学生にぜひ挑戦してもらいたいと思います。
お薦めの本
経済学はとっつきにくい分野だと感じている人も多いかと思いますが、研究の対象は多方面に広がっています。高校生にその広がりの面白さを分かってもらえるような、読み物を紹介します。
・『その問題、経済学で解決できます』、ウリ・ニーズィー/ジョン・A・リスト著、東洋経済新報社、2014年
・『0(ゼロ)ベース思考』、スティーブン・レヴィット/スティーブン・タブナー著、ダイヤモンド社、2015年
→『0(ゼロ)ベース思考』の前2作である、『ヤバい経済学』『超ヤバい経済学』スティーブン・レヴィット/スティーブン・タブナー著、東洋経済新報社(2007、2010年)もおススメです。
座談会を終えて(千野貴裕)
大学のグローバル化が叫ばれる昨今ですが、欧米の研究大学(こういう言い方も本当は嫌なのですが)では分野を超えた研究者のインフォーマル/フォーマルな交流が多く行われています。コーヒーやビール、食事をともにしつつ、お互いの考えに耳を傾け、共通の話題をもつことは自分の狭い知的関心を広げてくれます。今回の座談会を通して、公共市民学専修はまさにこうした機会を実現できる場所だとあらためて認識しました。公共的であること、市民的であることのひとつの意味は、自分と背景や考え方が異なる他者と一緒にともにやっていけること、つまり、他者に対してオープンでありながら、他者と共有できるルールを探すことだと思います。これは、事実としてますます多様になる現代社会を生きる上で強く求められることです。公共市民学専修では、分野を超えた合同ゼミの機会や、複数の教員を交えたトークセッションなど、improvisationalな知的活動の企画が多々進行中です。自分の専門分野をしっかり身につけるだけでなく、他分野の人と共通の言語を探す営みを通じて、より本来的な知的活動をやっていける、そういう専修にしていきたいと思います。
お薦めの本
齋藤純一『公共性』岩波書店。
現代公共性論の古典。在学生にはきちんと読んでほしいし、入学前にチャレンジするのはもっといいです。本当の力をつけるには、本と向き合う時間をたくさん取ってください。
福沢諭吉『学問のすゝめ』岩波文庫。
身分や出自によらず、学問は立身出世の機会を平等に与えてくれる――この本の趣旨をそう理解するのは正しいでしょう。しかしより重要なことは、学問が他者との共同の営みであることを指摘していることだと思います。
座談会を終えて(若林幹夫)
普段はそれぞれ違った対象を、違った方法で分析し、違った言葉で語っている4人が、「公共」、「市民」、「大学」といった共通の主題をめぐって掛け合う、インタープレイの楽しさを感じた座談会でした。「公共市民学」という名の学問は、いまだこの世に存在しません。それは教員・学生相互のインタープレイを通じて、これから現れてくるのだと思います。きちんとした主題の設定と、それをアドリブも交えて変奏していく技術が、そうした掛け合いには不可欠です。公共市民学専修を、そうした社会科学のインタープレイのできる、ライブ感覚溢れるステージにしていきたいですね。
お薦めの本
ハンナ・アレント『人間の条件』(志水速雄訳、ちくま学芸文庫)。
……public, private, socialという社会領域の違いから、人間の活動と世界のあり方を考える社会哲学の名書。ハッキリ言って難しい本ですが、人間と社会について考えるための鉱脈が幾つも隠された、何度も繰り返し読む価値のある本です。この本とユルゲン・ハーバーマス『公共性の構造転換』(細谷貞雄訳、未來社)が、公共市民学の古典としてまずあげられるべき本だと思います。
見田宗介『社会学入門――人間と社会の未来』(岩波新書)。
……「でも古典ってやっぱり難しくて」という人は、こちらから。初学者向けの入門書ですが、「人間の関係の学」としての社会学の大きな骨格を示すとともに、人類社会の未来を展望する骨太な本。公共市民学との関係では、「補 交響圏とルール圏――〈自由な社会〉の骨格構成」が必読です。「それでもやっぱり難しい」という人は、若林幹夫『社会学入門一歩前』(NTT出版)で思考の準備運動をしてみてください。
(2017年7月25日)

